旧市倉家住宅
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:781
旧市倉家住宅
施設概要

あきる野市指定有形文化財「旧市倉家住宅」

あきる野市五日市郷土館内
住所:〒190-0164 あきる野市五日市920-1(詳細地図)
電話:042-596-4069
開館時間:午前9時30分~午後4時30分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日が休館日)
年末年始(12月27日~1月4日)
入館料:無料
建物の沿革
市内の古い建物が生活様式の変化によって改造され、建て替えられて失われていく中、気候・風土にあわせて作られた一般的な農家は、昔ながらの暮しを今日に伝える資料としてとても重要なものとなっています。
旧市倉家住宅は、かつてあきる野市五日市 566番地にあり、平成元年と平成9年に行った文化財調査では、江戸時代末期の構造・形式をよく残し、建築の質の高さと当時の生活様式を伝える歴史資料として高く評価されました。また、養蚕技術の変遷を伝える構造や改造跡があり、保存状態も極めて良好であったことから、平成10年9月3日に市指定有形文化財(建造物)となり、平成11年4月にあきる野市に寄贈されたものです。
建物の概要
入母屋(いりもや)造りの茅葺きで、上屋桁行きが7.5間、梁行き3間です。内部は、北側の土間部と南側の床上部に分かれ、土間部には石組みのナガシの上に板敷床が張り出し、北西隅にカマドが造られたダイドコロとなります。
床上部は、表にザシキ ・ デイ、裏にオカッテ ・ ヘヤ ・ オクを配しています。平面形式は、田の字型に各部屋が配置された四間型(よつまがた)ですが、裏のオカッテとヘヤが分かれることから変形四間型となり、江戸時代末期から明治時代にかけての一般的な農家の形態を残しています。
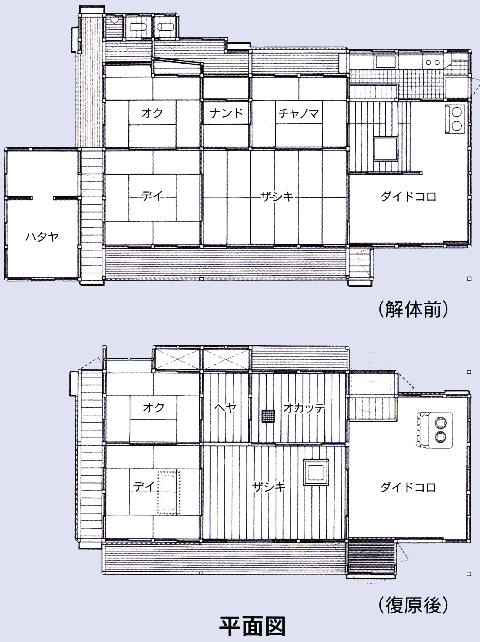
復原について
復原では、屋根材の茅・杉皮・竹のほか、土台・根太・貫など、腐っていたり強度が不足して使えない部材以外は旧材を使っています。柱や梁などの主要な木材は、腐朽した部分を切り取り、接ぎ木をして再使用しています。特にカマド北側の梁は、虫喰いが激しくホゾが効かなかったため、内部をくり抜いて人工木材で成型し、補強木材を組み込んでいます。
また、壁土は解体の時に集めておいた土に、新しい荒木田土と刻んだ藁を加えて発酵させたものを使いました。
このように、古い材料・天然の材料を上手に使い、昔ながらの技術で復原したものです。
解体の成果
解体工事の時に調査を行い、木を繋ぎ合わせる切込み(仕口)の状況や柱に刻まれた溝・釘跡、擦れた跡など、さまざまな痕跡から建設当時の構造や改造の状況を検討しています。
例えば、ザシキの東側とオカッテの西側には障子戸が立て込まれていましたが、敷居・鴨居に3本の溝があることから、雨戸2枚と障子戸1枚の古い形式に変更しました。ザシキ ― ヘヤ境の柱に押板がついていたと考えられる切込みが認められたため、これを復原しています。また、建物南・西側外の柱には、垂木掛けをとめた釘跡が見つかり、下屋を復原しています。
解体調査の後、礎石の下を発掘して改造の痕跡を探しました。フロバ溜め桶の痕跡や、ナガシ周りの石積み跡、胎盤を埋納したと思われる施設など、この建物に関連する痕跡のほか、さらに古い掘立柱建物跡や井戸跡なども見つかっています。
今回の復原では、フロバ溜め桶とナガシ周りの石積みを復原しています。
特徴
この建物の特徴は、上屋桁が上屋柱筋から東西 1.2尺、南北 1尺外に出ていることです。これは、地方寺院の本堂などに見られる出桁造りで、堂宮大工であった市倉治郎右衛門が自分の居宅に特殊な構造を取り入れたものと思われます。
お問い合わせ
電話: 文化財係(五日市郷土館 042-596-4069)
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます



